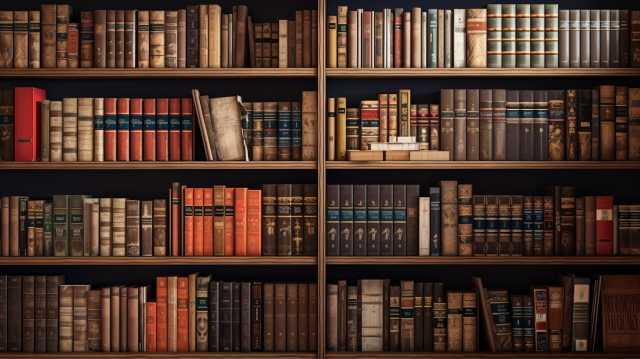
宮本茂の本
今年は偶然なのか、個人のゲームクリエイターに関する研究本がほぼ同じ時期に数冊出版されるという事態が起こりました。具体的には
『ゲームデザイナー 小島秀夫論』
『ゲームクリエイター 宮本茂』
『ゲーム作家 小島秀夫論』
の三冊です。上から順に発行された順番なのですが、まずはレジェンド中のレジェンド、ビデオゲームの父ともいえる偉大なゲームクリエイター、宮本茂氏の研究本を取り上げたいと思います。
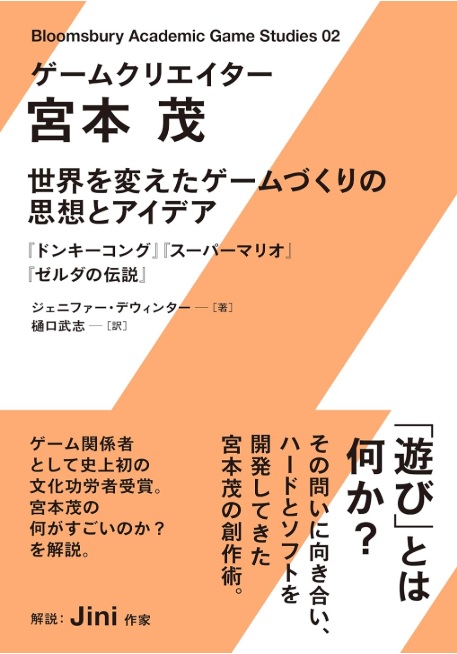
『ゲームクリエイター 宮本茂 世界を変えたゲームづくりの思想とアイデア』
ジェニファー・デウィンター (著)
作者はアメリカの大学教授、専攻はデジタル技術を用いたメディアコンテンツの開発と研究。この本のもとになったものも「南西部ポピュラー文化・アメリカ文化学会」のゲーム研究文科会ということで、内容としてはかなりアカデミックです。
きっかけはゲーム作品の精密な分析や、ゲーム開発についての研究などは多く見られたものの、作り手である個人に関する発表がほとんどなかったことだそうです。映画であれば監督、文学であれば作家に焦点があたるのに、ゲームではその傾向が少ない、と。そこで宮本茂の個人の業績をさかのぼっていくのですが、これがとてつもない領域の広さとタイトル数の多さにくらくらします。
ごく初期の作品である『ドンキーコング』などは、ゲームデザイン、アートなどいわゆるゲーム全てに携わるディレクター(当時はまだそんな言葉はありませんが)でわかりやすいのですが、任天堂という会社の特色でもある、ハードウェアとソフトウェア、両方に関わるのが宮本氏の天才性です。いわく、任天堂のハードウェアのコントローラー開発に多大な影響を与えてきたなどは他のゲームクリエイターではなしえなかったことでしょう。これはもともと宮本氏が大学でインダストリアル・デザインなどを学ばれていたことなども関係しているようです。
本書では宮本氏の出生、少年期、入社して間がないころの活動、そしてゲームソフトウェアとハードウェア両面での関わり、さらに広い領域でそもそものゲームの遊ばれ方のデザインなど、我々が想像するゲームデザイナーの業務範囲をはるかに超えた活躍が網羅的に取り扱われています。
残念ながら原書が本国で発売されたのは2015年ということで、最終章ではWii Uの苦戦で締めくくられていますが、2017年発売のNintendo Switchが驚異的な売り上げを誇り、任天堂が再度ビデオゲーム業界のトップに再臨したことはこの本が出る時点では誰も予想だにしなかったことでした。
学術的でやや難解な本書ですが、第5章に宮本氏が1999年にGDCで語った基調講演の内容がほぼ全文再掲されています。圧倒的にわかりやすく、かつ、今でも十分に通用するスピーチで、ゲームデザインに関する重要な視点、姿勢をいろんな事例とともに楽し気に語られています。この章は20ページくらいですが、正直、ここだけでも価値があります。読んで損なし、おススメです!
