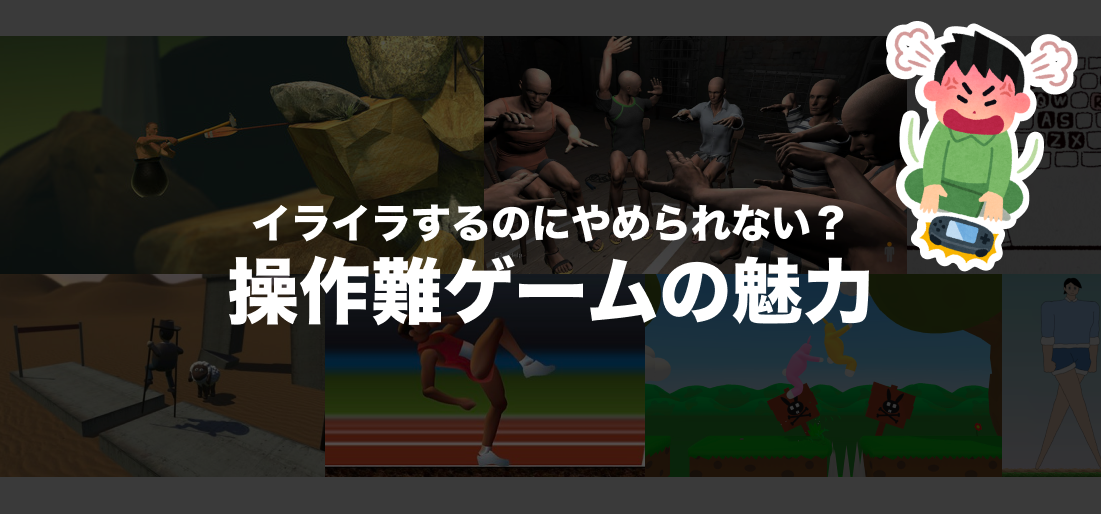
イライラするのにやめられない?操作難ゲームの魅力
プランナーの清水です。今回からプランナーのR&D雑記として「ゲームデザインについての研究」を開始します。様々なゲームがリリースされる中で、特定のジャンルに注目し、それがどうして面白いのか&人気なのかを分析していく内容になります。
第一回目の今回は「操作方法の難しさをコンセプトとするゲーム」です!(初回からニッチなジャンルすぎるかも……?)
長いので以降「操作難ゲーム」と呼ぶことにしましょう。どんなゲームだかイメージはつきますか?
「操作難ゲーム」とは?
ここで指している操作難ゲームとはどんなゲームなのか。イメージを掴んで頂くために、まず3つ作品を紹介します。
Getting Over It with Bennett Foddy
マウスカーソルと連動したハンマーで、壺に入ったキャラクターを動かして山を登るゲームです。シンプルな操作に聞こえますが、イメージ通りにキャラクターを動かすのは非常に難しく、少しのミスでスタート地点まで戻されてしまいます。

Hand Simulator
プレイヤーは人間の手を操作し、銃に弾を込める、釣りの餌をつける、爆弾を解除するといったシンプルなミッションに挑みます。指一本に対してキーが別々に割り当てられているため、手を動かすだけで5つのキーを操作しなければなりません。思い通りに動かないもどかしさと、一緒に遊んでいるプレイヤーのおかしな姿が爆笑を誘う作品です。

たけうまやろう (Stilt Fella)
竹馬に乗ったキャラクターを操作してゴールを目指すゲームです。左右の竹馬を右スティック左スティックで前後に、右トリガー左トリガーで上下に動かすことができます。段差を乗り越えたり穴を飛び越えたり、50を超えるバラエティ豊かなステージが待ち受けます。

他にも、膝関節と股関節をコントロールして100m走をするゲーム、前転後転とキックだけでゴールを目指す横スクロールアクションなど、「操作の難しさ」が遊びの核として作られたゲームは数多く存在します。なぜ「不親切」とも思われるこのようなジャンルの作品が数多くリリースされ、ゲーマーの中で一定の人気を獲得しているのでしょうか。
不親切で人を選ぶゲーム?
まず、この手のゲームの弱みから確認しましょう。ゲームを分解してクリアするまでにユーザーが乗り越えるべきステップを一般的なゲームと比較して考えてみます。

操作難ゲームは「ゲーム全体がシンプル」「最初から極端な難易度をプレイヤーに要求している」という傾向があります。一発ギャグや出オチのようなもので、幅広い遊びやプレイヤーの成長に合わせた親切なレベルデザインとは真逆のゲームと言えるでしょう。
その結果、プレイしてすぐに離脱してしまう人を生みやすいという弱点を持っています。買ってみたはいいけれどクリアできなくて諦めた、という作品、みなさんもありますよね……。
そんな「ユーザー逆フレンドリー」な操作難ゲームですが、数多くリリースされ、コンスタントに何かしらの作品が話題に上がります。致命的に見える欠点があるにも関わらず一定の人気を保つこのゲームジャンルにはどのような秘密があるのでしょうか。
操作難ゲームの強み① ユニークな操作性
これらのゲームは操作方法が非常にユニークです。
「右トリガーで弾を発射」「Wキーを押して前進」など、幅広いゲームでもはやスタンダードとなっている操作方法がありますが、これらのゲームはそこから大きく外れています。
これは慣れない操作方法を強要されるということでありストレスにもなるわけですが、大きなメリットにも繋がっています。
全てのユーザーに開かれた、真の公平性
FPSやRPGなど、特定のジャンルをやり込んでいるゲーマーは、似たような新作をプレイする際、経験値という大きなアドバンテージを持っています。しかし、操作難ゲームではそのアドバンテージは通用しません。それは操作方法がユニークすぎるから。FPSが得意な人も、格闘ゲームが得意な人も、ゲーム経験がほとんどない人も、皆が等しくゼロからのスタートになります。
「FPSは苦手だから……」「このジャンルは難しそう……」といった心理的ハードルが存在しないため、誰もが気軽に挑戦できる。これは、ユーザーにとって非常に大きなメリットです。
唯一無二だからこそ生まれる、強い中毒性
慣れ親しんだ操作方法と微妙に違う違和感。一般的なゲームでは、これがストレスにつながることがあります。「ドリフトした時に滑りが弱いなぁ」「スティックのカメラ操作がガクガクするなぁ」「やっぱり、こっちのゲームの方が慣れてるなぁ」と、元のゲームに戻ってしまうこともあるでしょう。
しかし、操作難ゲームほどスタンダードから離れてしまえば、比較対象がそもそも存在しません。さらに、一度その操作性を理解し快感を見出してしまうと、もう他のゲームでは満たすことができないのです。独特の体験が強い中毒性を生み出しています。

操作難ゲームの強み② 明快でタイパ重視のゲーム性
ユーザー不親切だ!と述べた段で、操作難ゲームは「ゲーム全体がシンプル」「最初から極端な難易度をプレイヤーに要求している」と書きました。しかし、これは裏を返せばメリットにもなっています。
一点集中の明快なゲーム性
操作難ゲームでは、操作を極端に難しくした結果、バランスを取るようにゲーム全体の構造を非常にシンプルにしていることが多いです。
一般的なゲームが「移動・攻撃・収集・育成・戦略」など、複数のファクターで難しさや歯応えを担保しているのに対し、操作難ゲームはゲーム全体の難易度を「操作」という一つのファクターに極振りしています。だからノイズとなる他の障壁はいらない。
操作難ゲームのプレイ映像を一目見ただけで「このゲームで何をすれば良いのか」という最大で唯一の課題を理解することができるはずです。
ゲーム性が明快というのは大きな強みです。ゲーム性がよくわからないゲームはそもそも購入しようという気持ちになりません。
すぐに本気でぶつかれる
ゲーマーの一定数はタイパ(タイムパフォーマンス)を重視する傾向がありますが、操作難ゲームはその需要に合った最適解の一つだと考えています。
操作という最初のステップが一番高い壁だと先に述べましたが、その結果プレイヤーはゲームを起動してすぐにその難しさを体験することができます。
ゲームを得意とするプレイヤーほど、ゲーム内で本気を出さなければいけない状況になるまで時間がかかります。チュートリアルや序盤の簡単なステージが億劫に感じることはありませんか?そのようなせっかちなゲーマーにとっては、最初から最大の課題に100%の力をぶつけられる操作難ゲームのテンポ感が心地よく感じるのかもしれません。
まとめ
一見不親切で理不尽に思える操作難ゲームですが、その「操作の難しさ」は強力なフックになっています。
ユニークな操作性は、既存のゲーム経験をリセットし、すべてのプレイヤーに公平なスタートラインを提供します。そして、一度その沼にハマると、他では味わえない中毒性を生み出します。
また、ゲームの第一歩である操作に難易度を極振りすることで、ゲーム全体の構造は非常にシンプルになり、プレイヤーはすぐに唯一かつ最大の課題に集中できます。これはタイパを重視する現代のゲーマーにとって、非常に魅力的なゲームデザインと言えるでしょう。
ゲーム実況やゲーム配信という文化がメインストリームとなった現在、操作方法に苦戦したり笑える失敗が溢れる操作難ゲームは、これからもさらに勢いをつけていくはずです。どんな斬新なゲーム体験が生まれていくのか楽しみですね!
